神奈川県中部の境川中流域に集中、源満仲や左馬頭義朝を祀る12社
鯖神社(さばじんじゃ)とは、神奈川県中部の境川中流域、横浜市泉区・瀬谷区、藤沢市北部、大和市南部にかけて現存12社、「サバ」と読む社名を持つ(あるいは過去に持っていた)神社である。
サバ神社、さば神社などとも総称されるが、鯖以外に左馬、佐婆、佐波とも表記される。現社名から見ると、鯖が3社、左馬が5社、佐婆が1社、佐波が1社、その他が2社。その他2社は近代以降、地名によって社号を改称したもの。
御祭神は源義朝が9社、源満仲が3社。語源については、源義朝が左馬頭(さまのかみ)だったためともいうが、諸説あり詳細は不明。義朝・満仲の件を含め、詳細は後述するが、下記がその12社の一覧である。

[祭神]源義朝
[住所]横浜市瀬谷区橋戸3-20-1
[電話]045-301-1306 - 諏訪社

[祭神]源義朝
[住所]横浜市泉区上飯田町2517
[電話]045-802-1370 - 御霊神社

[祭神]源義朝
[住所]横浜市泉区下飯田町1389
[電話]045-802-1370 - 御霊神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町705
[電話]045-802-1370 - 御霊神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町4811
[電話]045-802-1370 - 御霊神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町3253
[電話]045-802-1370 - 御霊神社

[祭神]源義朝
[住所]大和市上和田1168
[電話]046-263-7071 - 浅間神社

[祭神]源義朝
[住所]大和市下和田1110
[電話]046-263-7071 - 浅間神社
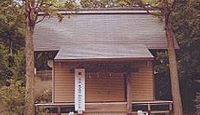
[祭神]源義朝
[住所]藤沢市高倉1128
[電話]0466-81-3175 - 御嶽大神

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市湘南台7-201
[電話]0466-81-3175 - 御嶽大神

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市石川141
[電話]0466-22-9210 - 白旗神社

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市西俣野821
[電話]-
満仲の孫が源頼義、曾孫が源義家で、源義家の曾孫が源義朝となる。
源義朝(みなもとのよしとも、1123年-1160年)は、平安時代末期の河内源氏の武将である。源為義の長男で、源頼朝・源義経らの父として知られる。
満仲は天寿を全うしたが、義朝は、東国武士団を率いて保元の乱で戦功を挙げ、左馬頭に任じられたものの、その3年後の平治の乱で敗北し、都を落ち延びる道中、尾張国で家人に裏切られ謀殺された。
これにより、義朝の子の頼朝は伊豆に流され、後の鎌倉幕府創設のために挙兵するまで、20年の時間を待たなければならなくなった。
鯖神社集中地域は、鎌倉にほど近く、頼朝の祖先筋に当たる武将を神々として奉斎することは理解できるものの、なぜ満仲と義朝なのか、それらが3社、9社なのか、全く不明。
そのため、現在では12社めぐりが盛ん。もともとは無病息災を祈る風習で、一日でこの七左馬をお参りすると疱瘡、麻疹(はしか)、百日咳などの悪病除けになるという。
「サバ参り」「相模七左馬」「相模七鯖」とも。
それによれば、もとは佐馬殿神社だった。その後、鯖神社に改称された。後に水害に遭い、再度改称して佐波神社になったという。
つまり、おそらくはすべての神社が左馬・佐馬を冠し、何らかの理由で義朝・満仲など源氏の祖を祀ったものだったが、江戸時代後期の『新編相模国風土記稿』ではいずれも「鯖」を称していたことから、左馬・佐馬→鯖になったものと考えられるか。
サバは、古くから日本人になじみの深い食用魚である。縄文時代の遺跡である青森県の三内丸山遺跡でブリなどとともにサバの骨が出土した。
平安時代には中男作物(地方産物を納めさせる税)として貢納され、また鯖売りの行商が行われていたなどという記録がある。
徳島県海陽町には、弘法大師(空海)を本尊とする鯖大師本坊(八坂寺)という寺がある。「鯖斷ち三年祈願」と言って、願掛けした後に鯖を三年間食べないことで、病気平癒・子宝成就・心願成就の御利益があると信じられている。
旅僧姿の弘法大師または行基が旅僧の姿で鯖を請うたのに、商人または馬子が荷物の鯖を与えなかったため罰せられたという伝説がある。
なお、鯖神社に関する考察については、柳田国男が有名。その著『石神問答』の中で「相模の左馬明神又は鯖明神」と、特異な神として指摘している。
また、『鯖大師』では、推量と断って、昔は、海岸近くの住民が取れた魚を、内陸のものと農産物を交易にいく時、境の神を祭り魚を供える風習があり、そこは道の辻森の下ほか、特別な感じがする隘路などで、そこには魚を載せるための石があり、それが霊地の目標ともなったという話が載っている。
どちらにしろ、武蔵国と相模国の違いはあるが、現在の神奈川県には、武蔵国の杉山神社、相模国の鯖神社と、特定地域に集中する神社・信仰が存在している。また、武蔵国と相模国をまたいで、御霊神社もある。これは他の都道府県ではほとんど例を見ないものとして、注目される。
【関連記事】
・神社いろいろ - 社格や形式などで神社を分類したまとめ - 神社めぐり全国編
サバ神社、さば神社などとも総称されるが、鯖以外に左馬、佐婆、佐波とも表記される。現社名から見ると、鯖が3社、左馬が5社、佐婆が1社、佐波が1社、その他が2社。その他2社は近代以降、地名によって社号を改称したもの。
御祭神は源義朝が9社、源満仲が3社。語源については、源義朝が左馬頭(さまのかみ)だったためともいうが、諸説あり詳細は不明。義朝・満仲の件を含め、詳細は後述するが、下記がその12社の一覧である。
瀬谷 左馬社

[祭神]源義朝
[住所]横浜市瀬谷区橋戸3-20-1
[電話]045-301-1306 - 諏訪社
上飯田 飯田神社

[祭神]源義朝
[住所]横浜市泉区上飯田町2517
[電話]045-802-1370 - 御霊神社
下飯田 鯖神社

[祭神]源義朝
[住所]横浜市泉区下飯田町1389
[電話]045-802-1370 - 御霊神社
鍋屋 鯖神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町705
[電話]045-802-1370 - 御霊神社
神田 佐婆神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町4811
[電話]045-802-1370 - 御霊神社
中之宮 左馬神社

[祭神]源満仲
[住所]横浜市泉区和泉町3253
[電話]045-802-1370 - 御霊神社
上和田 左馬神社

[祭神]源義朝
[住所]大和市上和田1168
[電話]046-263-7071 - 浅間神社
下和田 左馬神社

[祭神]源義朝
[住所]大和市下和田1110
[電話]046-263-7071 - 浅間神社
七ツ木郷 七ツ木神社
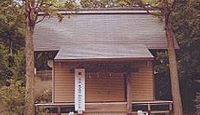
[祭神]源義朝
[住所]藤沢市高倉1128
[電話]0466-81-3175 - 御嶽大神
今田 鯖神社

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市湘南台7-201
[電話]0466-81-3175 - 御嶽大神
石川 佐波神社(藤沢市)

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市石川141
[電話]0466-22-9210 - 白旗神社
西俣野 左馬大明神

[祭神]源義朝
[住所]藤沢市西俣野821
[電話]-
源満仲と源義朝
源満仲(みなもとのみつなか、912年-997年)は、平安時代中期の武将である。清和源氏、六孫王経基の嫡男。多田源氏の祖で、多田満仲とも。多田神社の御祭神でもある。満仲の孫が源頼義、曾孫が源義家で、源義家の曾孫が源義朝となる。
源義朝(みなもとのよしとも、1123年-1160年)は、平安時代末期の河内源氏の武将である。源為義の長男で、源頼朝・源義経らの父として知られる。
満仲は天寿を全うしたが、義朝は、東国武士団を率いて保元の乱で戦功を挙げ、左馬頭に任じられたものの、その3年後の平治の乱で敗北し、都を落ち延びる道中、尾張国で家人に裏切られ謀殺された。
これにより、義朝の子の頼朝は伊豆に流され、後の鎌倉幕府創設のために挙兵するまで、20年の時間を待たなければならなくなった。
鯖神社集中地域は、鎌倉にほど近く、頼朝の祖先筋に当たる武将を神々として奉斎することは理解できるものの、なぜ満仲と義朝なのか、それらが3社、9社なのか、全く不明。
七さば巡り
ともかく、この鯖神社では古来より七さば巡りが盛ん。絶対に間違いない、といえる神社もいくつかあるものの、7社がどの鯖神社を指すかは諸説ある。そのため、現在では12社めぐりが盛ん。もともとは無病息災を祈る風習で、一日でこの七左馬をお参りすると疱瘡、麻疹(はしか)、百日咳などの悪病除けになるという。
「サバ参り」「相模七左馬」「相模七鯖」とも。
神社名について
これらの各社がどのような社名の変遷をたどってきたのか、諸説ある。中でも、佐波神社は社名変遷の由緒を伝えている。それによれば、もとは佐馬殿神社だった。その後、鯖神社に改称された。後に水害に遭い、再度改称して佐波神社になったという。
つまり、おそらくはすべての神社が左馬・佐馬を冠し、何らかの理由で義朝・満仲など源氏の祖を祀ったものだったが、江戸時代後期の『新編相模国風土記稿』ではいずれも「鯖」を称していたことから、左馬・佐馬→鯖になったものと考えられるか。
鯖に対する信仰
鯖に絡んで考えると、鯖稲荷と呼ばれた東京都港区東新橋の日比谷神社や、東京都中央区八丁堀の日比谷稲荷神社がある。サバは、古くから日本人になじみの深い食用魚である。縄文時代の遺跡である青森県の三内丸山遺跡でブリなどとともにサバの骨が出土した。
平安時代には中男作物(地方産物を納めさせる税)として貢納され、また鯖売りの行商が行われていたなどという記録がある。
徳島県海陽町には、弘法大師(空海)を本尊とする鯖大師本坊(八坂寺)という寺がある。「鯖斷ち三年祈願」と言って、願掛けした後に鯖を三年間食べないことで、病気平癒・子宝成就・心願成就の御利益があると信じられている。
旅僧姿の弘法大師または行基が旅僧の姿で鯖を請うたのに、商人または馬子が荷物の鯖を与えなかったため罰せられたという伝説がある。
柳田国男の考察など
どちらにしろ、よく分からないが、この集中している地域は昔から何らかの連帯があったことは間違いない。なお、鯖神社に関する考察については、柳田国男が有名。その著『石神問答』の中で「相模の左馬明神又は鯖明神」と、特異な神として指摘している。
また、『鯖大師』では、推量と断って、昔は、海岸近くの住民が取れた魚を、内陸のものと農産物を交易にいく時、境の神を祭り魚を供える風習があり、そこは道の辻森の下ほか、特別な感じがする隘路などで、そこには魚を載せるための石があり、それが霊地の目標ともなったという話が載っている。
どちらにしろ、武蔵国と相模国の違いはあるが、現在の神奈川県には、武蔵国の杉山神社、相模国の鯖神社と、特定地域に集中する神社・信仰が存在している。また、武蔵国と相模国をまたいで、御霊神社もある。これは他の都道府県ではほとんど例を見ないものとして、注目される。
【関連記事】
・神社いろいろ - 社格や形式などで神社を分類したまとめ - 神社めぐり全国編



コメント