樹木が生い茂る「暗がりの宮はん」江戸前期の本殿は市有形文化財
[住所]京都府京都市南区久世東土川町30
[電話]-
倉掛神社(くらかけじんじゃ)は、京都府京都市南区久世東土川町にある神社。現在は向日神社の兼務神社で、御朱印も向日神社で頂ける。
創祀・創建年代は不詳。一説に、天智天皇10年(671年)の創建とも。後に、東土川村の産土神として崇敬された。
御祭神は倉掛の神。倉掛神とも、倉掛大明神とも。五穀豊穣を守護する農耕神とされている。
もう一柱の御祭神は九面大明神(弁財天)で、智慧・福徳・財宝を授けてくださる有難い女神として、古くから篤い信仰を集めてきた。
本殿は江戸時代前期の寛文6年(1666年)3月の造営で、一間社春日造こけら茸、現在は覆屋の中に南面して建つ。市の有形文化財に指定されている。
本殿をはじめ、拝殿、末社、小祠などが建つ境内は、樹木が生い茂って鎮守の森としての景観を良くとどめているとされる。
近年まで大きな森と竹藪で昼なお暗く、「暗がりの宮はん」の通称で近郷近在に広く知られていた。
水溜まりが点在する中に細い道が通じていたが、狐狸が棲む不気味な場所としても知られ、夕刻ともなれば人通りは絶えたと伝わっている。
現在、交通量が激しい国道171号線から東へ入ってすぐのところにありながら、格好の緑の広場となっており、親しまれている。
この境内も、本殿の文化財指定と同時に文化財環境保全地区に指定されている。
なお、当社は1月に行われる近隣21社からなる乙訓鎮座神社巡りの一社である。
【ご利益】
五穀豊穣、学業・受験合格、開運招福、財運

【関連記事】
・乙訓鎮座神社巡り - 京都府の乙訓地方に鎮座する指定の神社21社を巡るイベント
・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧
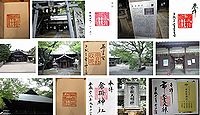
[電話]-
倉掛神社(くらかけじんじゃ)は、京都府京都市南区久世東土川町にある神社。現在は向日神社の兼務神社で、御朱印も向日神社で頂ける。
創祀・創建年代は不詳。一説に、天智天皇10年(671年)の創建とも。後に、東土川村の産土神として崇敬された。
御祭神は倉掛の神。倉掛神とも、倉掛大明神とも。五穀豊穣を守護する農耕神とされている。
もう一柱の御祭神は九面大明神(弁財天)で、智慧・福徳・財宝を授けてくださる有難い女神として、古くから篤い信仰を集めてきた。
本殿は江戸時代前期の寛文6年(1666年)3月の造営で、一間社春日造こけら茸、現在は覆屋の中に南面して建つ。市の有形文化財に指定されている。
本殿をはじめ、拝殿、末社、小祠などが建つ境内は、樹木が生い茂って鎮守の森としての景観を良くとどめているとされる。
近年まで大きな森と竹藪で昼なお暗く、「暗がりの宮はん」の通称で近郷近在に広く知られていた。
水溜まりが点在する中に細い道が通じていたが、狐狸が棲む不気味な場所としても知られ、夕刻ともなれば人通りは絶えたと伝わっている。
現在、交通量が激しい国道171号線から東へ入ってすぐのところにありながら、格好の緑の広場となっており、親しまれている。
この境内も、本殿の文化財指定と同時に文化財環境保全地区に指定されている。
なお、当社は1月に行われる近隣21社からなる乙訓鎮座神社巡りの一社である。
【ご利益】
五穀豊穣、学業・受験合格、開運招福、財運

【関連記事】
・乙訓鎮座神社巡り - 京都府の乙訓地方に鎮座する指定の神社21社を巡るイベント
・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧
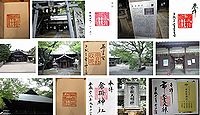


コメント