昭和期に伏見稲荷を勧請、駅名や地名が変更、関東一円からの信仰
[住所]東京都西東京市東伏見1-5-38
[電話]042-461-1125
東伏見稲荷神社(ひがしふしみいなりじんじゃ)は、東京都西東京市東伏見にある神社。近代社格では無格社。参拝すれば、御朱印を頂ける。
関東地方の稲荷神を信仰する信者たちの希望により、昭和4年(1929年)に稲荷神の総本社である伏見稲荷大社から御分霊を勧請して創建された。
伏見稲荷大社の御祭神の中から、宇迦御魂大神・佐田彦大神・大宮能売大神の3柱を勧請し、この3座を「東伏見稲荷大神」と総称している。
社地は、当時当地一帯を保有していた西武鉄道から無償貸与があったという。京から見て東への奉遷になるため、現社号となった。
東伏見という地名はこの神社ができてからの地名で、それにあわせて西武新宿線の駅名も上保谷から東伏見に変更された。
実際には東伏見駅と、西武柳沢駅の中間当たり、青梅街道と、当然当社が名称の由来となったであろう伏見通りの交差点近くに鎮座する。
戦前、中島飛行機の社員研修所があり、鍛錬教育が行われていた。このため、中島飛行機武蔵野製作所でなくなった人々の慰霊碑がある。
勧請の新しさからか、規模は大きいが近代社格で社格が与えられることはなく、無格社のままだった。
現在では、東の伏見稲荷として、関東一円から参拝があり、境内に乱立する多くの朱色の鳥居が、その信仰の深さをうかがわせている。
例祭は2月初午の日。4月10日と10月20日に大祭があり、国の重要無形民俗文化財に指定されている「江戸の里神楽」などが奉納される。
境内地の北には伏見公園が広がり、朱色の社殿が境内の緑に映えて美しく、新東京百景の一つに選ばれている。
【ご利益】
商売繁盛、家内安全、厄災除け(公式HP)

【関連記事】
・東京都の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、東京都に鎮座している神社の一覧
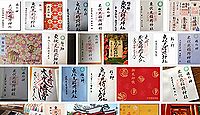
[電話]042-461-1125
東伏見稲荷神社(ひがしふしみいなりじんじゃ)は、東京都西東京市東伏見にある神社。近代社格では無格社。参拝すれば、御朱印を頂ける。
関東地方の稲荷神を信仰する信者たちの希望により、昭和4年(1929年)に稲荷神の総本社である伏見稲荷大社から御分霊を勧請して創建された。
伏見稲荷大社の御祭神の中から、宇迦御魂大神・佐田彦大神・大宮能売大神の3柱を勧請し、この3座を「東伏見稲荷大神」と総称している。
社地は、当時当地一帯を保有していた西武鉄道から無償貸与があったという。京から見て東への奉遷になるため、現社号となった。
東伏見という地名はこの神社ができてからの地名で、それにあわせて西武新宿線の駅名も上保谷から東伏見に変更された。
実際には東伏見駅と、西武柳沢駅の中間当たり、青梅街道と、当然当社が名称の由来となったであろう伏見通りの交差点近くに鎮座する。
戦前、中島飛行機の社員研修所があり、鍛錬教育が行われていた。このため、中島飛行機武蔵野製作所でなくなった人々の慰霊碑がある。
勧請の新しさからか、規模は大きいが近代社格で社格が与えられることはなく、無格社のままだった。
現在では、東の伏見稲荷として、関東一円から参拝があり、境内に乱立する多くの朱色の鳥居が、その信仰の深さをうかがわせている。
例祭は2月初午の日。4月10日と10月20日に大祭があり、国の重要無形民俗文化財に指定されている「江戸の里神楽」などが奉納される。
境内地の北には伏見公園が広がり、朱色の社殿が境内の緑に映えて美しく、新東京百景の一つに選ばれている。
【ご利益】
商売繁盛、家内安全、厄災除け(公式HP)

【関連記事】
・東京都の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、東京都に鎮座している神社の一覧
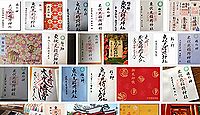


コメント
コメント一覧 (2)