平安初期の創建、聖護院の守護神、節分は「火の用心のお札」
[住所]京都府京都市左京区聖護院山王町43
[電話]075-771-4054
熊野神社(くまのじんじゃ)は、京都府京都市左京区聖護院山王町にある神社。京都十六社朱印めぐり、京都三熊野の一社で、参拝すれば、東山区の新熊野神社と同様、熊野三山の象徴ともなっている八咫烏の印が入った御朱印を頂ける。
御祭神は伊弉冉尊、伊弉諾尊、天照大神、速玉男尊、事解男尊の五柱。
平安時代の弘仁2年(811年)、修験道の日圓上人が国家鎮護のために紀州の熊野大神を勧請したことに始まると言われている。
寛治4年(1090年)に創立された聖護院は当社を守護神とし、別当職を置いて当社の管理を行った。
熊野信仰が盛んだった平安末期、後白河法皇は度々熊野御幸を行うとともに、当社を厚く崇敬し、紀州の土砂や樹木を用いて、社頭の整備に力を注いだ。
室町時代には足利義満から広大な社地を寄進され、社域は鴨川に至るものとなった。その後も歴代天皇に崇敬され、庶民の信仰も集めたが、応仁の乱により荒廃した。
江戸時代の寛文6年(1666年)、衰微を嘆いた聖護院宮道寛法親王によって再興された。道寛親王はやはり荒廃していた新熊野神社も再興している。
天保6年(1835年)には大修造が行われ、現在の本殿は、その時に賀茂御祖神社(下鴨神社)の旧本殿を移築したもの。本殿は平成19年(2007年)に修理が行われている。
大正元年(1912年)の市電丸太町線の開通、昭和元年(1926年)の東大路通りの拡幅などにより、社域が縮小して、現在の社域となった。
例祭は5月16日。4月29日には神幸祭が行われ、大小の神輿が渡御する。大神輿は光格天皇の寄進によるもの。
古くから節分の日に「火の用心のお札」を受ける風習があり、多くの参拝者で賑わう。
当社から領布される守護符・熊野牛王宝印は、中世以降広く流布して、盗難災除、病気平癒などの霊験があるとして尊重され、また起請誓紙として用いられている。
北区小松原北町に熊野神社衣笠分社がある。
【ご利益】
縁結び、安産、健康長寿、病気平癒、鎮火

【関連記事】
・京都三熊野 - 後白河法皇が整備した京の熊野神社三社、熊野三山同様に本宮・新宮・那智
・京都十六社朱印めぐり - 年頭の記念品が頂ける京都府京都市と周辺の16社巡礼イベント
・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧
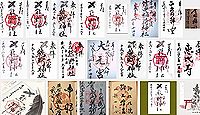
[電話]075-771-4054
熊野神社(くまのじんじゃ)は、京都府京都市左京区聖護院山王町にある神社。京都十六社朱印めぐり、京都三熊野の一社で、参拝すれば、東山区の新熊野神社と同様、熊野三山の象徴ともなっている八咫烏の印が入った御朱印を頂ける。
御祭神は伊弉冉尊、伊弉諾尊、天照大神、速玉男尊、事解男尊の五柱。
平安時代の弘仁2年(811年)、修験道の日圓上人が国家鎮護のために紀州の熊野大神を勧請したことに始まると言われている。
寛治4年(1090年)に創立された聖護院は当社を守護神とし、別当職を置いて当社の管理を行った。
熊野信仰が盛んだった平安末期、後白河法皇は度々熊野御幸を行うとともに、当社を厚く崇敬し、紀州の土砂や樹木を用いて、社頭の整備に力を注いだ。
室町時代には足利義満から広大な社地を寄進され、社域は鴨川に至るものとなった。その後も歴代天皇に崇敬され、庶民の信仰も集めたが、応仁の乱により荒廃した。
江戸時代の寛文6年(1666年)、衰微を嘆いた聖護院宮道寛法親王によって再興された。道寛親王はやはり荒廃していた新熊野神社も再興している。
天保6年(1835年)には大修造が行われ、現在の本殿は、その時に賀茂御祖神社(下鴨神社)の旧本殿を移築したもの。本殿は平成19年(2007年)に修理が行われている。
大正元年(1912年)の市電丸太町線の開通、昭和元年(1926年)の東大路通りの拡幅などにより、社域が縮小して、現在の社域となった。
例祭は5月16日。4月29日には神幸祭が行われ、大小の神輿が渡御する。大神輿は光格天皇の寄進によるもの。
古くから節分の日に「火の用心のお札」を受ける風習があり、多くの参拝者で賑わう。
当社から領布される守護符・熊野牛王宝印は、中世以降広く流布して、盗難災除、病気平癒などの霊験があるとして尊重され、また起請誓紙として用いられている。
北区小松原北町に熊野神社衣笠分社がある。
【ご利益】
縁結び、安産、健康長寿、病気平癒、鎮火

【関連記事】
・京都三熊野 - 後白河法皇が整備した京の熊野神社三社、熊野三山同様に本宮・新宮・那智
・京都十六社朱印めぐり - 年頭の記念品が頂ける京都府京都市と周辺の16社巡礼イベント
・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧
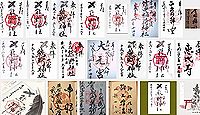


コメント