古来から御神体の国宝・神剣を信仰対象とする、土佐国二宮 巨木「燈明杉」
[住所]高知県高岡郡日高村下分1794
[電話]0889-24-7466
小村神社(おむらじんじゃ)は、高知県高岡郡日高村にある神社。国史見在社で、土佐国二宮、近代社格では県社。参拝すれば、御朱印を頂ける。
御祭神は国常立命(くにとこたちのみこと)。大地形成・生命活動の原動力をなす神とされる。国宝に指定されている「金銅荘環頭大刀」を御神体とする。中世における本地仏は大日如来だった。
社伝では、第31代用明天皇2年(587年)の創建とする。『土佐幽考』では、『新撰姓氏録』に見える高岳首・日下部と高岡郡日下庄とを関連づけ、その共通の祖神として国常立命を祀り大刀を御神体としたとする。
別説では、越智国造の小知命(小千命/乎致命)の墓が今治市の「日高」に伝わること等から、この小知命が当地に至り、国土開発の神として国常立命を祀り、大刀を御神体としたとする。
国史では、『日本三代実録』に「小村神」の神階が貞観12年(870年)に従五位下から従五位上に昇叙された旨の記載が見える。しかし『延喜式神名帳』には記載がない。
当社に残された仁治元年(1240年)・貞和3年(1347年)の棟札によると、当社の修理・造替には古くは国司があたったが、次第に地頭があたるようになったとし、仁淀川中流・上流域の吾河山・別府山・横川山がその用材供給地であった。
また、その貞和3年の棟札に「正一位二宮小村大天神」と見え、中世には当社は土佐国一宮の土佐神社(高知市一宮)に次ぐ二宮に位置づけられた。
以降は蓮池城(現・土佐市)城主の大平氏から保護を受け、文亀3年(1503年)には大平国雄から三十六歌仙図が奉納された。
戦国時代には頭屋組織によって神事が運営されるようになり、天文12年(1543年)の御頭帳には11の御頭屋敷が記されている。
また天正16年(1588年)の「日下之別符地検帳」では、日下村全域や隣の波川村にもわたる神田の記載があるほか、宮床・馬場は検地が免除された。
江戸時代に入ると、土佐国に入った山内氏により上述の社領が没収され、慶長6年(1602年)の知行割において与えられたのは神田の2反と別当寺への2反のみだった。
その別当寺は神宮寺で、「小村山昭光院神宮寺」と称していたが明治の廃仏毀釈で廃寺となった。
明治元年(1868年)2月に近代社格制度において県社に列し、「小村大天神」などと称されていた社名を明治3年(1870年)に正式に現社号とした。
その後いつしか社格は一旦郷社に下っていたが、大正13年(1924年)に県社に再昇格した。
現在の社殿は、江戸時代中期の宝永2年(1705年)の造営。本殿・幣殿・拝殿から成る複合社殿で、本殿は流造銅板葺、この本殿前に接続する幣殿・拝殿は平面に「十」字形を成し、屋根は同じく銅板葺である。
いわゆる「出蜻蛉(でとんぼ)」形式。
樹齢1000年といわれる、樹高25メートル、胸高直径270センチメートルを測る巨木「燈明杉」がある。
宝永2年(1705年)の仁淀川洪水や、安政元年(1854年)の安政南海地震、日露戦争などの異変に際して梢に霊火が点灯したという伝承に基づく命名。
摂末社には、仁井田神社、曽我五郎・曽我十郎を祀り、曽我兄弟にまつわる「瀬登りの太刀」伝説を伝える剱神社、秋葉神社、飛地境内社として、若宮神社と水神社がある。
11月15日が秋季大祭。氏子から代表して頭人(当人)が選ばれ、頭人の家(頭家、当家)で頭家祭を行なった後、頭家から「おなばれ」と称される神幸行列が出、大太鼓を打ち鳴らしながら神輿とともに村内を練り歩く。
御神体で、国宝の「金銅荘環頭大刀拵・大刀身(こんどうそうかんとうたちごしらえ・たちのみ)」は、古墳時代末期(飛鳥時代)の7世紀前半に作られた、直刀(反りのない片刃の刀)とその外装。
11月15日の秋季大祭時にのみ公開される。
平安時代後期作の「木造菩薩面 2面」が国の重要文化財(彫刻)に指定されているほか、県や村の文化財は多数。
【ご利益】
国家安泰・立身出世、家内安全・五穀豊穣・祈願成就の神

【関連記事】
・国宝が伝わる神社 - 所蔵、所有、由来している美術工芸品が国宝に指定されている神社
・国史見在社 - 『延喜式』に先行する六国史に記載のある神社で、式外社を指すことが多い
・高知県の旧県社 | 府県社とは? - 旧県社(縣社)・旧府社、その都道府県の中で有力な神社
・高知県の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、高知県に鎮座している神社の一覧
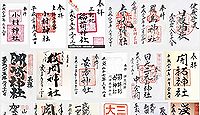
[電話]0889-24-7466
小村神社(おむらじんじゃ)は、高知県高岡郡日高村にある神社。国史見在社で、土佐国二宮、近代社格では県社。参拝すれば、御朱印を頂ける。
御祭神は国常立命(くにとこたちのみこと)。大地形成・生命活動の原動力をなす神とされる。国宝に指定されている「金銅荘環頭大刀」を御神体とする。中世における本地仏は大日如来だった。
社伝では、第31代用明天皇2年(587年)の創建とする。『土佐幽考』では、『新撰姓氏録』に見える高岳首・日下部と高岡郡日下庄とを関連づけ、その共通の祖神として国常立命を祀り大刀を御神体としたとする。
別説では、越智国造の小知命(小千命/乎致命)の墓が今治市の「日高」に伝わること等から、この小知命が当地に至り、国土開発の神として国常立命を祀り、大刀を御神体としたとする。
国史では、『日本三代実録』に「小村神」の神階が貞観12年(870年)に従五位下から従五位上に昇叙された旨の記載が見える。しかし『延喜式神名帳』には記載がない。
当社に残された仁治元年(1240年)・貞和3年(1347年)の棟札によると、当社の修理・造替には古くは国司があたったが、次第に地頭があたるようになったとし、仁淀川中流・上流域の吾河山・別府山・横川山がその用材供給地であった。
また、その貞和3年の棟札に「正一位二宮小村大天神」と見え、中世には当社は土佐国一宮の土佐神社(高知市一宮)に次ぐ二宮に位置づけられた。
以降は蓮池城(現・土佐市)城主の大平氏から保護を受け、文亀3年(1503年)には大平国雄から三十六歌仙図が奉納された。
戦国時代には頭屋組織によって神事が運営されるようになり、天文12年(1543年)の御頭帳には11の御頭屋敷が記されている。
また天正16年(1588年)の「日下之別符地検帳」では、日下村全域や隣の波川村にもわたる神田の記載があるほか、宮床・馬場は検地が免除された。
江戸時代に入ると、土佐国に入った山内氏により上述の社領が没収され、慶長6年(1602年)の知行割において与えられたのは神田の2反と別当寺への2反のみだった。
その別当寺は神宮寺で、「小村山昭光院神宮寺」と称していたが明治の廃仏毀釈で廃寺となった。
明治元年(1868年)2月に近代社格制度において県社に列し、「小村大天神」などと称されていた社名を明治3年(1870年)に正式に現社号とした。
その後いつしか社格は一旦郷社に下っていたが、大正13年(1924年)に県社に再昇格した。
現在の社殿は、江戸時代中期の宝永2年(1705年)の造営。本殿・幣殿・拝殿から成る複合社殿で、本殿は流造銅板葺、この本殿前に接続する幣殿・拝殿は平面に「十」字形を成し、屋根は同じく銅板葺である。
いわゆる「出蜻蛉(でとんぼ)」形式。
樹齢1000年といわれる、樹高25メートル、胸高直径270センチメートルを測る巨木「燈明杉」がある。
宝永2年(1705年)の仁淀川洪水や、安政元年(1854年)の安政南海地震、日露戦争などの異変に際して梢に霊火が点灯したという伝承に基づく命名。
摂末社には、仁井田神社、曽我五郎・曽我十郎を祀り、曽我兄弟にまつわる「瀬登りの太刀」伝説を伝える剱神社、秋葉神社、飛地境内社として、若宮神社と水神社がある。
11月15日が秋季大祭。氏子から代表して頭人(当人)が選ばれ、頭人の家(頭家、当家)で頭家祭を行なった後、頭家から「おなばれ」と称される神幸行列が出、大太鼓を打ち鳴らしながら神輿とともに村内を練り歩く。
御神体で、国宝の「金銅荘環頭大刀拵・大刀身(こんどうそうかんとうたちごしらえ・たちのみ)」は、古墳時代末期(飛鳥時代)の7世紀前半に作られた、直刀(反りのない片刃の刀)とその外装。
11月15日の秋季大祭時にのみ公開される。
平安時代後期作の「木造菩薩面 2面」が国の重要文化財(彫刻)に指定されているほか、県や村の文化財は多数。
【ご利益】
国家安泰・立身出世、家内安全・五穀豊穣・祈願成就の神

【関連記事】
・国宝が伝わる神社 - 所蔵、所有、由来している美術工芸品が国宝に指定されている神社
・国史見在社 - 『延喜式』に先行する六国史に記載のある神社で、式外社を指すことが多い
・高知県の旧県社 | 府県社とは? - 旧県社(縣社)・旧府社、その都道府県の中で有力な神社
・高知県の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、高知県に鎮座している神社の一覧
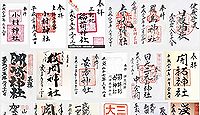


コメント