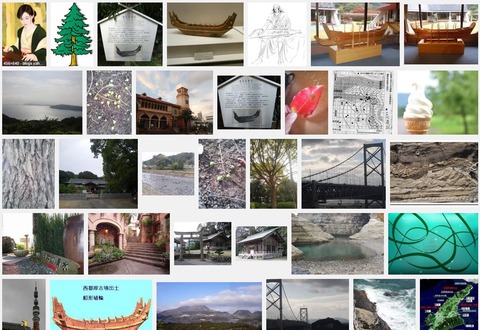 14.仁徳天皇
14.仁徳天皇14-7.枯野という船
仁徳天皇の御世のことですが、兔寸河(ときがわ)の西に一本の高い木があり、この木の影は、朝日が当たると淡路島まで届き、夕日が当たると、高安山を超えました。
そこで、この木を切って船を作ったところ、船足がものすごく速かったので、その船を枯野(からの)と名付け、毎日、淡路島から冷たい水を汲んで、天皇のお使いになる水として献上しました。
この船が壊れたので、塩を作るための薪にして使い、焼け残った木で琴を作ったところ、その音は七里四方まで鳴り響きました。その当時、人々が歌った歌。
これは、そういう木がありました、ということで、明確な聖天子伝説とはいいがたい部分もあるかもしれませんが、この説話から受ける印象として、マイナスイメージはありません。
仁徳天皇自身、女運(と言うか、チョーコエー・カミさん。愛人は、みんな性格がよさそう~)的には微妙ですが、統治的にはまずまずだった、ということを、この説話は示しているのでしょうか。
※画像は、「枯野という船」Google画像検索結果のキャプチャー
【関連記事】
・等乃伎神社 - 『古事記』の巨木伝説と太陽信仰、町村合併で市内鬼門に鎮座
・楠本神社(岸和田市) - 仁徳紀の巨樹の根元に鎮座、木魂→船玉を奉斎する古社
・畠山篤『河内王朝の山海の政―枯野琴と国栖奏』 - 山人と海人の生業の繁栄を呪祷する神事
【古事記の神・人辞典】
・履中天皇


コメント