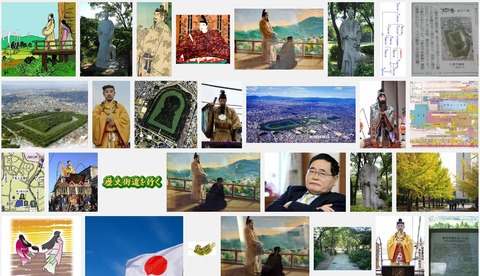 14.仁徳天皇
14.仁徳天皇14-1.聖王伝説
天日矛(あめのひぼこ)に絡む伝説が続きましたが、本編に戻って、応神天皇が亡くなった後、弟の宇遅能和紀郎子(うじのわきのいらつこ=和紀郎子)と皇位を譲り合いましたが、和紀郎子が早くに亡くなったために即位した、応神天皇の子の大雀命(おおさざきのみこと)、つまり仁徳天皇のお話へ。
 仁徳天皇はある時、高い山に登って、四方の国を見て曰く。
仁徳天皇はある時、高い山に登って、四方の国を見て曰く。仁徳天皇「夕方だというのに、国中に、かまどの煙が立っていない。民はみな貧しいのであろう。これから三年の間は、人民の税と使役をすべて免除して、国を富ませなくてはなるまい」
と言って、その通り税と使役を免除したので、天皇の御殿も破れ崩れて、ひどく雨が漏りましたが、少しも修理させようとせず、木の箱で雨を受け、雨の漏らないところに移って、生活しました。
三年たって、また国中を見ると、かまどの煙は、国に満ちていました。やっと人民が豊かになったと思って、もう大丈夫、と、税と使役を再び科すことにしました。
だから民は栄えて、税や使役に苦しむことはありませんでした。それゆえ、人々はこの天皇の御世を称えて、聖の帝の御世と言いました。
しっかし、出木杉っというか、仁徳天皇のほかの節ではすべて歌が挿入され、女好き、歌好きのイメージが強いのに対して、この逸話には歌が出てこない。。たまたまか、はたまた。どちらにしろ、古事記の仁徳天皇の逸話の中では異色の部類に入りそうです。
※画像は、「仁徳天皇 かまどの煙」Google画像検索結果のキャプチャー。
【関連記事】
・若宮八幡大神宮 - 蒲生の若宮さん、大坂冬の陣で佐竹義宣が本陣、10月にだんじり
【関連キャラ】
・仁徳天皇 - 古事記中盤の主役はやはり女好きの御仁
【古事記の神・人辞典】
・仁徳天皇
・カツラギソツヒコ
・イワノヒメ
・履中天皇
・スミノエノナカツ
・反正天皇
・允恭天皇
・カミナガヒメ
・オオクサカ
・ワカクサカ
・ヤタノ
・ウジノワカイラツメ


コメント